父の実家がある県には看護科のある高校がある。
当時高校生だった従兄の彼女の友人がその学校に通っていて、校内ではまことしやかに語られている怪談がいくつかあるという。
その怪談の一つを、語ろうと思う。
その高校は本物の病院での実習がある。
もちろんほんの手伝い程度のことしかできないらしいが、先輩看護師の仕事ぶりを見てその憧れを強くする者もいれば、あまりのハードさに自信を無くしてしまう者もいるらしい。
ある日、一人の学生が夜勤の実習を受けていた時のことだ。
先輩看護師とともに真夜中の見回りを済ませ、彼女はふと、自分の持っていた懐中電灯を忘れてしまったことに気付く。
看護師に断りを入れ、心当たりのある場所を探すために暗闇の廊下を歩いて行く。借りてきた懐中電灯の明かりだけがその廊下を照らしている。
おそらく、見回り途中に寄ったトイレの手洗い場。
そこを目指して彼女は歩いて行く。
こつん、こつん。
自分の足音がやけに響く。
こつん、こつん。──こつん。
空耳かと思って足を止めたのは、自分の足音以外にもう一つの足音が聞こえたような気がしたからだ。
もしかしたら看護師が心配して追いかけてきてくれたのかもしれない、そう思って振り返ってみたけれど、誰もいない。
彼女は再び歩き出す。
こつん、こつん。──こつん、こつん。
きっと、静かな院内に、自分の足音が反響しているだけだ。
そう思い先を急ぐ。
こつん、こつん。
目指すトイレの前まで来ると、少し先の廊下に人がいた。
白衣を着た看護師だった。
──もしかしたら先輩だろうか? いつの間に自分を追い抜いたのだろう? それとも別のフロアの看護師?
彼女その看護師に声をかけようとして、足を止めた。
──なぜ、あの看護師は懐中電灯を持っていないのだろう。こんなに真っ暗な院内で。
そう思った瞬間ぞっとして、彼女は後ずさる。
気付かれてはいけない、と反射的に思った。
視線の先の看護師が、こちらを振り向こうとした。彼女は慌てて懐中電灯を消し、トイレに駆け込み個室の一つに入り、鍵をかけてうずくまる。
──あれはきっと、この世のものではない。
この話は怖かったですか?
怖いに投票する 4票
コメント(2)
※コメントは承認制のため反映まで時間がかかる場合があります。




























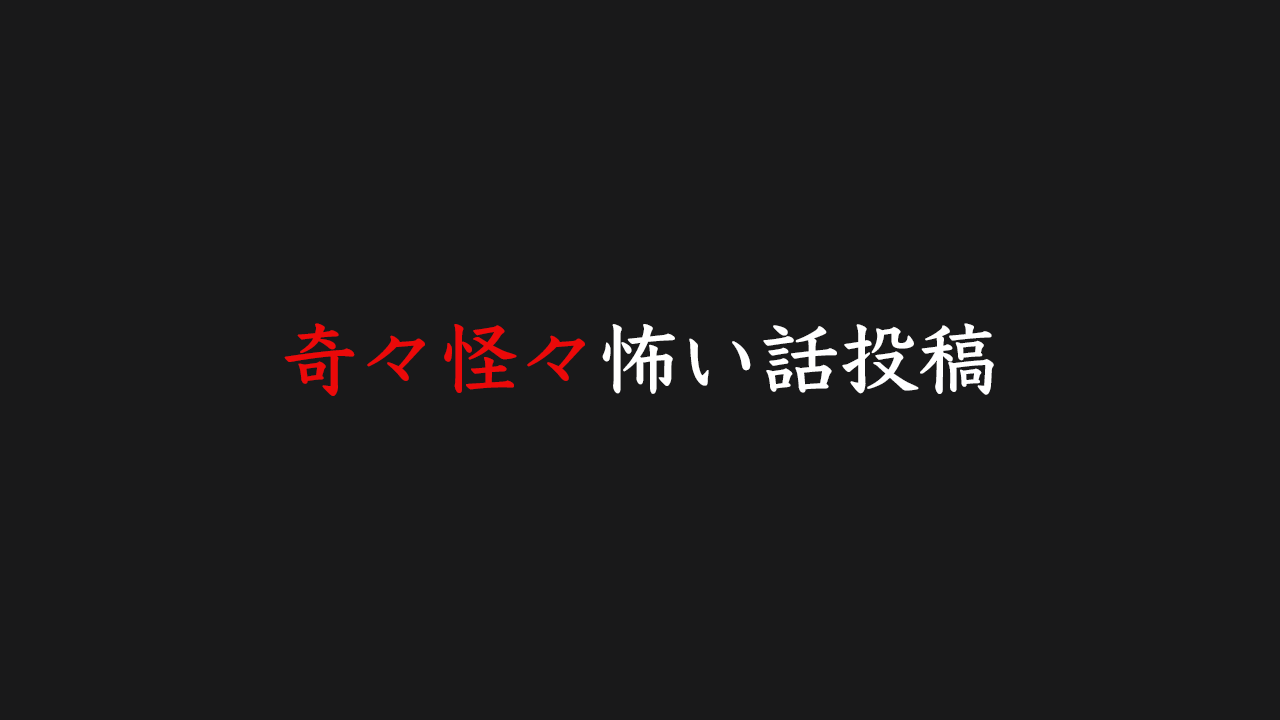



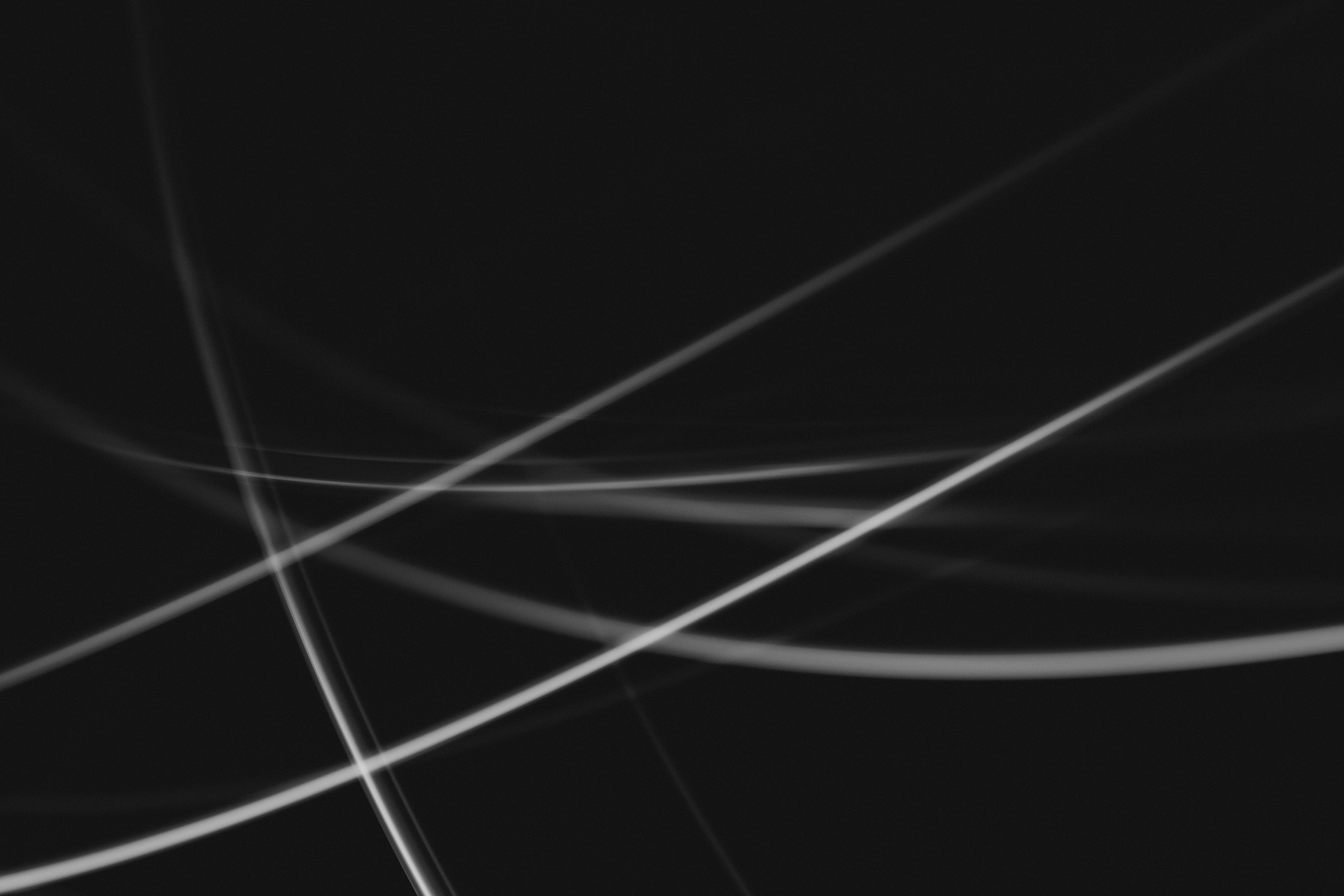


高校生の実習生は夜勤なんてしないよー
顔ないのに覗きこんだんだ!
こわいのかな?
いたずらだろね!